【完全ガイド】電気工事士とは?仕事内容・資格・キャリアまで徹底解説
2025年10月10日
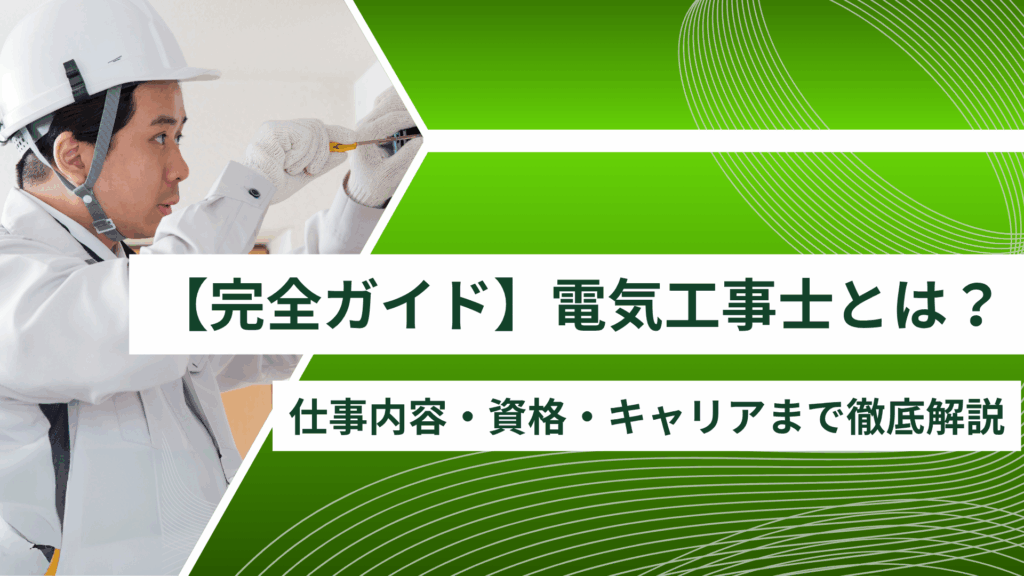
電気工事士ってどんな資格?
電気工事士は、住宅やビル、工場、公共施設など幅広い建物の電気設備工事を適正に行うために必要な国家資格です。単なる工事作業ではなく、法律に基づいた資格制度として位置づけられており、照明設備やコンセントの設置、高圧受電設備まで幅広い設備工事に対応します。これらの工事は、人命や財産を守るために高い安全性と確実性が求められるため、無資格者による作業は禁止されています。
また、国内では多くの資格保有者が活躍しており、その重要性は年々増しています。社会インフラを支える仕事として将来性も高く、一生モノの技術と知識を身につけられる点が大きな魅力です。特に省エネ住宅や再生可能エネルギー設備など新しい分野でも需要が拡大しており、若い世代から中高年まで幅広い年齢層にとってキャリアの選択肢となる資格と言えるでしょう。
電気工事士とは?その役割と重要性
電気工事士は、住宅や商業施設における低圧電力設備から、工場やビルの高圧電力設備まで、さまざまな電気設備工事を担当します。低圧とは一般家庭で使われる100ボルト・200ボルトの電気設備を指し、高圧とは600ボルト以上の電力設備を指します。これらは単に「配線をつなぐだけ」の仕事ではなく、安全基準や施工方法が細かく法律で定められており、誤った施工は感電や火災など重大事故を引き起こすリスクがあります。そのため、電気工事士法によって有資格者による施工が義務付けられているのです。
電気工事士の役割は、建物の安全性と機能性を守ることだけではありません。停電が発生した際の復旧作業や、設備更新に伴うリニューアル工事、さらにはエネルギー効率を高める最新設備の導入工事まで幅広く対応します。社会的にも非常に重要な技術職であり、公共性の高い仕事と言えるでしょう。
どんな現場で活躍できる?(住宅から高圧設備まで)
電気工事士が活躍する現場は実に多彩です。一般住宅の配線工事やリフォーム時の電気設備更新はもちろんのこと、マンションやビルの共用部設備、店舗やオフィスの照明・空調設備の設置工事などが代表的な仕事です。それだけでなく、学校や病院といった公共施設、さらには工場や大型商業施設での受変電設備工事なども電気工事士の仕事範囲となります。
たとえば住宅現場であれば、コンセント増設や照明交換といった比較的小規模な工事が中心ですが、工場現場では数千ボルト規模の高圧設備を扱うこともあり、より高度な知識と技術が必要です。このように担当する現場の規模や種類によって仕事内容が大きく変わるため、自身のキャリアプランや得意分野に合わせて活躍の場を選べるのも電気工事士の魅力です。いずれの現場でも、社会のインフラを支える縁の下の力持ちとして、安定した需要と活躍の場を持つ職業であることに変わりはありません。
電気設備工事ではどんな仕事をしているの?1日の流れと現場の工程
電気設備工事とは
電気設備工事とは、建物で電気を安全に使えるようにするための配線や機器の設置、点検、試験などの作業を指します。新築住宅の電気配線から、リフォーム時の設備更新、さらには太陽光発電やEV充電器などの新しい設備への対応まで、幅広い工事が含まれます。
建物の種類や用途によって必要な設備は異なるため、現場ごとに施工内容を柔軟に調整する必要があります。たとえば高圧設備を扱う工場では高度な技術が求められますし、住宅では美観や使い勝手も重要になります。
こうした作業を、安全かつ確実に行うためには専門知識と国家資格が不可欠です。電気工事士は、社会インフラを支える技術者として欠かせない存在といえるでしょう。
電気設備工事の具体的な工程と技術ポイント
電気設備工事は、計画から仕上げまで複数の工程で構成されます。以下は代表的な流れです。
① 施工図の確認:建物の図面をもとに、配線ルートや機器の位置を決定します。
② 仮設電源の確保:工事用の電源を仮設置し、安全に作業できる環境を整えます。
③ 配線ルートの準備:天井や壁に穴をあけ、配線用の管や通路を整備します。
④ ケーブル配線:電線を通して固定し、接続部分も丁寧に処理します。
⑤ 機器の取り付け:スイッチ、コンセント、照明などの器具を設置します。
⑥ 試験・検査:配線ミスや漏電がないかをチェックし、通電確認を行います。
⑦ 仕上げと報告:カバーを取り付けて見た目を整え、写真と報告書で完了を記録します。
こうした工程を確実にこなすには、丁寧な施工と高い安全意識が欠かせません。特に配線の内部処理や最終仕上げの美しさも、プロとしての技術が問われるポイントです。
現場での一日の仕事の流れ(例:住宅配線工事の場合)
電気工事士の現場では、効率的に作業を進めるために一日の流れがある程度定型化されています。以下は、一般的な住宅配線工事の1日を例にしたスケジュールです。
・8:00 現場集合・朝礼・作業内容の確認
・8:30 養生作業・道具の準備・安全確認
・9:00 配線ルートの確認・穴あけ・ボックス設置
・10:00 休憩
・10:30 ケーブルの配線・固定作業
・12:00 昼休憩
・13:00 機器の取り付け(スイッチ・コンセント・照明器具など)
・15:00 休憩
・15:30 午後の作業の続き(器具の取り付け)
・16:00 通電確認・試験
・17:00 片付け現場終了・解散
第2種電気工事士と第1種電気工事士の違い
第2種と第1種はどちらも社会に必要とされる資格ですが、その活躍のフィールドや求められるスキルには明確な違いがあります。将来的により規模の大きな現場に携わりたい方や、リーダー職を目指して専門性を高めたい方は、第一種電気工事士取得を視野に入れることが重要です。自身の目指すキャリアや関わりたい現場の規模感を考えたうえで、適切な資格取得を目指すことが、長く安心して働き続けるための第一歩となります。
第2種電気工事士とは?できること・活かせる場面
第2種電気工事士は、主に一般住宅や小規模な店舗など、日常生活に身近な場所で使用される600ボルト以下の低圧設備工事を行うための国家資格です。たとえば、住宅のコンセントや照明設備の取り付け、エアコンの設置や換気扇の配線工事などがその代表的な業務です。身近な施設で必要となる電気設備工事のほとんどがこの範囲に含まれるため、第二種電気工事士は生活インフラを支える重要な技術者として、建設業界や設備管理業界で幅広く活躍しています。
この資格は比較的取得しやすいとされており、電気工事の世界に初めて挑戦する方にとって最初のステップとして位置づけられています。学科試験と技能試験を経て免状が交付されますが、専門的な学校に通わずとも独学で合格を目指すことも十分可能です。菅原電工でも、未経験から入社した社員が半年から1年ほどで第二種電気工事士資格を取得し、現場で必要とされる技術者として一人前に育っていくケースが数多くあります。
第二種電気工事士を取得することで、比較的小規模な現場ながらも実際の施工業務に携わることができるようになります。自分の手で配線を整え、電気設備を正常に動かすことで、目に見える形で人々の生活を支えている実感を得られるのもこの仕事のやりがいの一つです。未経験から一歩踏み出すには非常に適した資格と言えるでしょう。
第1種電気工事士とは?できること・求められるスキル
第1種電気工事士は、600ボルトを超える高圧設備を含む工事を行える上位資格であり、第二種電気工事士では対応できない大型施設や工場、公共施設などの電気工事も担うことができる国家資格です。対象となる工事範囲は非常に広く、工場やビルの受変電設備、商業施設の動力設備、さらには発電設備や公共インフラ関連の高圧電力設備工事まで含まれます。
求められる技術や知識も第二種とは比べ物にならないほど高度であり、単に配線作業を行うだけでなく、電気設備全体の設計や安全管理、トラブル発生時の対応まで幅広いスキルが必要とされます。法律や安全基準に関する理解も不可欠であり、作業ミスが重大事故につながる可能性もあるため、より高い責任感を持って業務にあたる必要があります。
そのため、第一種電気工事士の取得は簡単ではありませんが、その分仕事の幅が大きく広がり、収入面やキャリア形成においても大きなメリットがあります。菅原電工でも第一種資格保有者は特に重要なポジションを担っており、大型案件や工場設備工事のリーダー職として活躍する社員が多く在籍しています。実際に第一種を取得した社員の中には、施工管理職や技術責任者としてキャリアアップを果たし、現場全体を統括する立場に就くケースも珍しくありません。
電気工事士資格を持つメリットとは
電気工事士資格を取得することで、仕事の幅が広がるだけでなく、収入やキャリア形成、そして将来の安定性まで、さまざまなメリットを得ることができます。資格を取得するまでには学習や試験といったステップが必要になりますが、それに見合う価値が確実にある国家資格です。ここでは、電気工事士資格を持つことで得られる具体的なメリットについて、3つの観点から詳しく解説していきます。
①就職・転職での有利さ
電気工事士資格を保有していると、建設業界や設備工事関連の求人において非常に高い評価を受けます。求人票を見ても、「電気工事士資格必須」と条件に明記されているものが多く、資格の有無によって応募できる仕事の選択肢そのものが大きく変わってきます。特に第二種電気工事士の場合は住宅や小規模店舗の工事を中心に、第一種電気工事士の場合は工場や大型商業施設まで対応できることから、より高い条件での採用が期待できます。
また、未経験者であっても資格取得済みであれば採用されやすくなることが大きなポイントです。実際に現場経験がない方でも、資格を持っているというだけで採用後の研修期間が短縮され、より早く実務に入れるといったメリットがあります。菅原電工でも資格取得者は実務経験がなくても積極的に採用しており、現場補助や簡単な作業からスタートし、段階的に経験を積みながらスキルアップできる環境を整えています。資格をきっかけに新たなキャリアを切り開きたい方にとっては、非常に有利な条件が揃っているといえるでしょう。
②資格手当・キャリアアップの可能性
電気工事士資格を取得することで得られるもうひとつの大きなメリットは、資格手当の支給やキャリアアップの道が広がることです。多くの電気工事会社では、資格取得者に対して毎月の給与とは別に資格手当を支給する制度を設けています。手当の具体的な金額は企業や地域によって異なりますが、菅原電工でも電気工事士資格取得者に対して手当制度を設け、社員一人ひとりの努力をしっかりと評価しています。こうした手当は月々の収入を安定させるだけでなく、資格を取るためのモチベーションにもつながります。
また、資格を活かしてキャリアアップを目指すことも十分可能です。現場スタッフからスタートし、現場リーダーや施工管理職へとステップアップし、さらには管理職や技術責任者へと昇進する流れが一般的です。特に第一種電気工事士資格を取得した場合は、工場や大型施設の高圧設備工事を担当できるため、より大きな案件や責任あるポジションを任される機会が増えます。資格と経験を積み重ねることで、自分自身の働き方をより自由に選べるようになるのも、この仕事ならではの魅力です。
③「手に職」の安心感と将来性
電気工事士は、景気変動や社会情勢に左右されにくい「手に職」型の仕事としても知られています。住宅や商業施設、公共インフラの電気設備は常に必要とされるものですから、電気工事の需要がなくなることはほとんどありません。実際、コロナ禍や景気後退局面でも、電気工事業界は一定の需要を維持し続けています。
さらに、近年では太陽光発電設備やEV(電気自動車)充電設備など、新しい分野でも活躍の場が広がっています。再生可能エネルギーや省エネ設備の普及が進む中、電気工事士の仕事はますます多様化しており、時代の流れに応じた成長が期待できる職種です。技術と資格を身につければ、一生涯にわたって活躍できる場があるという安心感は、他の職業にはない大きな強みといえるでしょう。
また、資格を活かして独立・フリーランスとして活躍する道もあります。一定の経験と実績を積めば、小規模ながら自営業として開業し、顧客を獲得して自分のペースで仕事をすることも可能です。実際に年間売上1,000万円以上を目指す方も少なくなく、自分自身のスキルを武器に安定した収入を得ることができます。将来的に独立を視野に入れている方にとっても、電気工事士資格は強力な武器となるでしょう。
資格取得までのステップガイド
電気工事士資格を取得するためには、学科試験と技能試験という2つのステップをクリアする必要があります。難しそうに感じる方もいるかもしれませんが、流れをきちんと理解したうえで計画的に学習を進めれば、未経験からでも十分合格が目指せます。ここでは申し込みから免状交付までの手順をわかりやすく解説します。
学科試験について
電気工事士試験の最初の関門となるのが学科試験です。試験では電気理論や配線設計、電気設備に関する法令、安全管理など幅広い知識が問われます。とくに初心者にとってはオームの法則や電力計算といった電気理論が難しく感じることもありますが、最初から難しい問題に取り組むより、まずはテキストで基礎を理解することが大切です。
学習時間の目安は第二種電気工事士で100〜150時間、第一種電気工事士で150〜200時間程度です。1日1〜2時間の勉強をコツコツ積み重ねれば、半年以内で合格レベルに達することが可能です。菅原電工では、社内で勉強会を定期的に実施しており、資格取得を目指す社員同士で学び合いながら、実務に直結する知識もしっかりと身につけられる環境を整えています。
技能試験について
学科試験をクリアした後は技能試験に進みます。技能試験は実技形式で、実際の工具や材料を使って指定された配線作業を制限時間内に完成させる必要があります。第二種電気工事士の場合は一般住宅向けの基本的な配線が中心ですが、第一種ではより複雑な高圧設備工事も含まれるため、求められる技術レベルも上がります。
技能試験に合格するためには、何よりも手を動かして練習することが重要です。市販されている練習キットを利用し、実際の試験課題と同じ配線作業を繰り返し行うことで、自然と手順や工具の扱いが身につきます。特に技能試験は40〜60分という限られた時間内で作業を終える必要があるため、スピードと正確さの両方が求められます。
試験日・申し込みから免状交付までの流れ
電気工事士試験は春期・秋期の年2回実施されています。受験申し込みは春試験の場合は2〜3月頃、秋試験の場合は8〜9月頃が受付期間です。試験日は春が5月〜7月、秋が10月〜12月となっており、地域や試験種別によって多少前後することがあります。
試験は学科試験と技能試験が別日に行われ、どちらも合格することで晴れて資格取得となります。その後、各都道府県の担当窓口で免状交付申請を行います。必要書類としては、合格通知、顔写真、住民票、申請書類一式が必要で、手数料の支払いも伴います。申請から免状が手元に届くまでには、通常1か月前後かかります。
菅原電工の資格取得支援制度について
菅原電工では、電気工事士資格を目指す方や、すでに資格をお持ちの方を積極的に採用しています。第二種電気工事士資格を取得していれば、未経験からのチャレンジも歓迎しています!
また、社員一人ひとりが安心して働き、長く活躍できるよう、資格取得支援制度やキャリア形成のサポート体制を充実させています。
「資格は持っているけれど、現場で本当にやっていけるのか不安…」と感じるのは、多くの方が最初に抱く気持ちです。実際、入社直後には「試験勉強で学んだ内容と、現場の仕事はまったく違う」と戸惑うような声もよく聞かれます。
でも、ご安心ください。現場では、経験豊富な先輩がそばについて、作業の一つひとつを丁寧に教えてくれます。未経験からでも、日々の業務の中で少しずつスキルを身につけていくことができます。
今では現場を任される立場になったベテラン社員も、最初は何もわからない未経験からのスタートでした。「はじめは右も左も分からなかったけれど、先輩の指導や現場経験を積む中で、自然とできることが増えていった」と語っています。
こうした現場経験を積みながら、将来的には、第一種電気工事士など上位資格の取得も視野に入れながら、専門性の高い現場へのステップアップも可能です。
さらに、資格取得後は手当が支給される制度も整っており、日々の努力がしっかりと評価される仕組みとなっています。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ・ご応募について】
菅原電工では、まずは話を聞いてみたいという方からのご連絡も歓迎しています。ご興味をお持ちの方は、以下の募集ページをご覧のうえ、お気軽にお問い合わせ・ご応募ください。
【選考の流れ】
① 電話面接
② 本社での対面面接
「まずは話だけ聞いてみたい」「自分にできるか不安」という方も大歓迎です。どうぞお気軽にご連絡ください。
電気工事の世界に初めて飛び込む方も、次のステップを目指す有資格者の方も、どちらも大切な仲間としてお迎えしています。まずはお話だけでも構いません。ぜひ一度、私たちにご相談ください。皆さまからのご応募・お問い合わせを心よりお待ちしております。
